農業営業を成功させるための戦略とアプローチ方法を徹底解説

農業業界は日本の基幹産業でありながら、従来の営業手法では成果を上げにくい特殊な業界です。
本記事では、農業業界の特徴を理解し、効果的な営業アプローチ方法について詳しく解説します。
農業関連事業に携わる営業担当者や、農業市場への参入を検討している企業の方に向けて、実践的な営業戦略をお伝えします。
農業の業界について
日本の農業は総産出額約8兆7,000億円の重要な基幹産業です。しかし、農業経営体数は約103万にまで減少し、農業就業人口の68%が65歳以上という深刻な高齢化が進行しています。
一方で、スマート農業の導入やICT技術の活用により、生産性向上と効率化への取り組みが本格化しています。
日本の農業市場規模と現状
日本の農業総産出額は約8兆7,000億円(2023年時点)で、GDP全体に占める割合は約1.2%となっています。
主要な品目別では米が約1兆5,000億円、野菜が約2兆3,000億円、畜産物が約3兆円を占めており、食料自給率はカロリーベースで約38%という水準です。
農業経営体数は約103万経営体まで減少しており、1970年代の約550万戸から大幅に減少が続いています。
一方で、一経営体あたりの経営規模は拡大傾向にあり、法人経営体の数は約3万法人まで増加するなど、農業の構造変化が進んでいます。
農業従事者の高齢化と後継者問題
農業就業人口は約136万人まで減少し、そのうち65歳以上が約68%を占める深刻な高齢化が進行しています。
基幹的農業従事者の平均年齢は約68歳となっており、10年前と比較して約2歳上昇しています。
新規就農者数は年間約5万人で推移していますが、離農者数がそれを大幅に上回る状況が続いています。
特に49歳以下の新規就農者は約1万2,000人程度にとどまっており、持続可能な農業経営の継承が大きな課題となっています。
後継者不足により、優良な農地が耕作放棄地となるケースも増加しており、全国の耕作放棄地面積は約28万ヘクタールに達しています。
スマート農業の導入動向
政府は2025年までにスマート農業の本格的普及を目標に掲げ、現在全国で約400地区のスマート農業実証プロジェクトが実施されています。
GPS機能付きトラクターの自動走行システムは約3,000台、ドローンによる農薬散布は約1万5,000台が導入されています。
IoTセンサーを活用した環境モニタリングシステムや、AIを活用した病害虫診断アプリなども普及が始まっており、特に施設園芸分野での導入が進んでいます。
しかし、導入コストの高さや操作の複雑さから、中小規模農家での普及率はまだ10%程度にとどまっている状況です。
農業業界の抱える課題
現在の農業業界は人手不足、収益性の悪化、気候変動への対応、販売チャネルの多様化という4つの重要な課題に直面しています。
特に労働力確保の困難さと生産コスト上昇による経営圧迫が深刻化しており、持続可能な農業経営の実現に向けた抜本的な対策が急務となっています。
人手不足と労働力の確保
農業の現場では深刻な人手不足が続いており、特に収穫期や田植え期などの繁忙期における労働力確保が困難になっています。
外国人技能実習生や特定技能外国人の受け入れが増加しているものの、全体の労働力不足を補うには至っていません。
季節労働者の確保も年々困難になっており、時給1,000円以上での募集でも人材が集まらない地域が増加しています。
このため、機械化による省力化や作業効率の向上が急務となっていますが、設備投資の負担が農家経営を圧迫するケースも多く見られます。
収益性の改善と経営効率化
農産物価格の低迷と生産資材費の高騰により、農業経営の収益性悪化が深刻化しています。
特に燃料費や肥料費、飼料費の上昇により、生産コストが大幅に増加している一方で、農産物の販売価格は据え置きまたは下落傾向にあります。
小規模農家では経営の多角化や6次産業化による付加価値向上が求められていますが、マーケティング知識や販売ノウハウの不足により、思うような成果を上げられないケースが多く見られます。
また、デジタル化による経営管理の効率化も遅れており、データに基づいた経営判断ができていない農家が大多数を占めています。
気候変動への対応
近年の異常気象により、農作物の品質低下や収量減少が頻発しています。
猛暑による高温障害、集中豪雨による冠水被害、干ばつによる水不足など、従来の栽培技術では対応しきれない気象条件が常態化しています。
特に果樹や茶葉などの永年作物では、気候変動の影響により適地が北上する現象が見られ、産地の再編成が必要となっています。
また、新たな病害虫の発生や既存病害虫の発生時期・被害程度の変化により、防除体系の見直しも求められています。
流通・販売チャネルの多様化
消費者の購買行動の変化やEC市場の拡大により、従来のJA出荷や市場流通だけでは十分な販路確保が困難になっています。
直販や産直、インターネット販売など多様な販売チャネルへの対応が求められていますが、個々の農家では対応力に限界があります。
また、食品安全性や環境配慮への関心の高まりにより、GAP認証や有機JAS認証などの取得が求められるケースが増加していますが、認証取得・維持にかかるコストと労力が農家の負担となっています。
農産業における主要なセグメントと効果的なアプローチ
農業業界は耕種農業、畜産業、農業法人、農協・JAという主要なセグメントに分かれており、それぞれ異なる特徴とニーズを持っています。
効果的な営業活動のためには、各セグメントの課題と求める解決策を深く理解し、個別最適化されたアプローチ戦略を展開することが重要です。
耕種農業(米作・野菜・果樹)へのアプローチ
米作農家に対しては、省力化と品質向上の両立を重視したアプローチが効果的です。
田植機や収穫機械の高性能化、スマート農業技術の活用による作業効率改善を軸とした提案が求められます。
また、食味向上や特別栽培米への転換支援なども重要なポイントとなります。
野菜農家では、周年安定生産と市場ニーズへの対応が重要課題です。
施設園芸では環境制御システムの導入による収量・品質の向上、露地野菜では機械化による労働負荷軽減や土壌管理技術の改善提案が有効です。
果樹農家に対しては、高品質果実の安定生産と労働負荷軽減が主要なニーズとなります。
剪定や摘果作業の省力化技術、病害虫防除の効率化、貯蔵・出荷調整技術の向上などを中心とした提案が効果的でしょう。
畜産業へのアプローチ
酪農家では、個体管理の高度化と労働環境の改善が重要なテーマとなっています。
搾乳ロボットや発情発見システム、飼料給与の自動化システムなど、ICT技術を活用した提案が有効です。
また、牛舎環境の改善による乳質向上や繁殖成績改善も、重要なアプローチポイントです。
肉用牛農家に対しては、飼養管理の効率化と肉質向上を軸とした提案が求められます。
TMR(完全混合飼料)調製システムや体重測定システム、健康管理システムなどの導入といった、生産性向上を図る提案が効果的です。
養豚・養鶏業では、疾病対策と生産性向上が最重要課題となっています。
衛生管理システムの強化、環境制御による快適性向上、AI技術を活用した個体管理システムなどの提案が有効です。
農業法人・企業農家へのアプローチ
大規模農業法人に対しては、経営効率化とデータ活用による最適化提案が重要となります。
ERPシステムの導入による経営管理の高度化、圃場管理システムによる作業効率向上、品質管理システムの構築などが主要なアプローチポイントです。
企業農家では、投資対効果を明確に示すことが重要です。導入コストに対する収益改善効果を定量的に示し、投資回収期間を明確にした提案が求められます。
また、既存システムとの連携性や拡張性も重要な検討要素となります。
法人化を検討している農家に対しては、法人化のメリットと課題を整理し、段階的な規模拡大や経営改善の道筋を示すことが効果的です。
農協・JAへのアプローチ
農協・JAに対しては、組合員農家全体の課題解決に貢献する提案が重要となります。
営農指導の効率化システム、農家向け情報提供システム、共同利用施設の効率化システムなどが主要なアプローチポイントです。
また、JAグループの広域合併が進む中で、統一的なシステム導入や標準化への対応も重要な提案要素となります。
複数のJAで共同利用できるシステムや、段階的な導入が可能なソリューションが求められています。
購買事業や営農指導事業の効率化を通じて、組合員サービスの向上とコスト削減を両立する提案が効果的です。
農産業における有効なアプローチ方法
農業営業の成功には信頼関係構築、季節性を考慮したタイミング戦略、実証データの活用、地域密着型の営業活動という4つの要素が不可欠です。
特に農家との長期的な信頼関係を築き、農閑期を狙った適切なタイミングでの提案活動が営業成果向上のカギとなります。
信頼関係構築の重要性
農業業界では、長期にわたる信頼関係の構築が営業成功の最重要要素となります。
農家は代々続く経営を行っているケースが多く、新しい技術や製品の導入には慎重な判断を行います。そのため、一度の訪問で成約に至ることはまれで、継続的な関係構築が不可欠です。
信頼関係を築くためには、農家の現状と課題を深く理解し、技術的な専門知識を持って具体的なアドバイスを提供することが重要です。
売り込みではなく、農家の経営改善パートナーとしての姿勢を示すことで、長期的な信頼を獲得できます。
また、約束した訪問時間の厳守、アフターフォローの確実な実施、トラブル時の迅速な対応など、基本的な信頼を積み重ねることが重要です。
農村地域では口コミの影響が大きいため、一度信頼を失うと地域全体での評判に影響することも念頭に置く必要があります。
季節性を考慮したタイミング戦略
農業は季節性の強い産業であり、作物の種類や地域によって忙しさの差が明確に存在します。
営業活動では、農家の作業スケジュールを十分に把握し、適切なタイミングでアプローチすることが重要です。
春の種まき・定植期、夏の管理作業期、秋の収穫期は農家がもっとも忙しい時期となるため、この期間の営業訪問は避けるべきです。
一方、冬期間や梅雨時期などの農閑期は、じっくりと話を聞いてもらえる絶好の機会となります。
また、次年度の計画立案時期(12~2月)や補助事業の申請時期(2~3月)などは、設備投資や新技術導入の検討が活発になるため、重点的な営業活動を行うべき時期です。
補助金活用の提案も併せて行うことで、導入決定の確率を高めることができます。
実証データを活用した提案手法
農家は経験に基づく判断を重視する傾向が強いため、新しい技術や製品を導入する際には、具体的な実証データの提示が不可欠です。
収量向上効果、品質改善効果、コスト削減効果などを数値で明確に示すことで、導入効果への理解と確信を得ることができます。
地域の気候条件や栽培条件に近い環境での実証事例を提示することが特に重要です。
他地域での成功事例だけでなく、同一県内や近隣地域での事例があれば、より説得力のある提案となります。
また、実証圃場の設置や試験導入の提案も効果的なアプローチ方法です。小規模での試験的な導入を通じて効果を実感してもらうことで、本格導入への道筋を作ることができます。
リスクを最小限に抑えた試験導入の提案は、農家の導入ハードルを下げる有効な手法です。
地域密着型の営業活動
農業は地域に根差した産業であり、地域の農業関係者とのネットワーク構築が営業成功のカギとなります。
普及指導員、JA営農指導員、農業改良普及センター職員などの農業関係者との良好な関係を築くことで、農家への紹介機会が増加します。
地域の農業関連イベントや研修会への積極的な参加も、重要な営業活動の一環です。
農機展示会、品評会、技術講習会などの場では、多くの農家と接触する機会があり、効率的な営業活動が可能となります。
また、地域の農業課題や特産品について深く理解し、地域農業の発展に貢献する姿勢を示すことで、地域全体からの信頼を獲得できます。
単なる販売活動ではなく、地域農業の発展パートナーとしての位置づけを確立することが、長期的な営業成功につながります。
農産業における営業ならFAXDMがおすすめ
農業従事者の多くは中高年層で構成されており、従来型の情報伝達手段を好む傾向があります。
FAXDMは農家の生活パターンに適合し、詳細な技術情報を確実に伝達できる効果的な営業手法です。適切なリスト作成と原稿制作により、高い営業効果を期待できます。
農業従事者にFAXDMが効果的な理由
農業従事者の多くは50代以上の中高年層が占めており、デジタルツールよりも従来型の情報伝達手段を好む傾向があります。
FAXは農家にとってなじみ深い通信手段であり、重要な情報を確実に受け取れる信頼性の高いツールとして認識されています。
農家の多くは早朝から夕方まで農作業に従事しており、電話での営業は作業の妨げになることが多いため敬遠されがちです。
一方、FAXであれば農家の都合のよい時間に内容を確認でき、じっくりと検討することができます。
また、農業関連の技術情報や製品情報は複雑な内容が多く、口頭での説明だけでは十分に伝わりにくい場合があります。
FAXであれば図表や詳細な説明を含めた情報提供が可能で、農家が後から見返すことができる点も大きなメリットです。
FAXDM成功のためのリスト作成方法
効果的なFAXDMを実施するためには、ターゲットとなる農家を適切に選定したリスト作成が重要です。
作物種類、経営規模、法人・個人の別、地域などの属性情報を整理し、自社の商品・サービスにマッチした農家をリストアップする必要があります。
農業経営体データベースや農業センサスのデータを活用することで、詳細な条件での絞り込みが可能となります。
また、展示会や説明会の参加者名簿、既存顧客からの紹介情報なども有効なリソースとなります。
リストの精度向上のためには、定期的な情報更新が不可欠です。離農や規模縮小により営業対象から外れる農家もあれば、新規就農や規模拡大により新たなターゲットとなる農家も存在します。
年1回程度のリスト見直しを行い、常に最新の情報に基づいた営業活動を心がけることが重要です。
農業向けFAXDMの原稿作成のポイント
農業向けFAXDMの原稿では、冒頭で農家にとってのメリットを明確に示すことが重要です。
「収量○○%向上」「作業時間○○%削減」「コスト○○%削減」など、具体的な数値を用いて効果を訴求することで、農家の関心を引くことができます。
技術的な説明は専門用語を適度に使用しながらも、分かりやすい表現を心がける必要があります。
農家は専門知識を持っていますが、新しい技術については詳しくない場合も多いため、導入効果と使用方法を簡潔に説明することが重要です。
また、実際の導入事例や成功体験談を掲載することで、信頼性と説得力を高めることができます。同じ地域や類似した経営条件の農家の事例があれば、より効果的な訴求が可能となります。
最後に、問い合わせ先や詳細資料請求の方法を明確に記載し、次のアクションにつなげる仕組みをつくることが重要です。
送信タイミングと頻度の最適化
FAXDMの送信タイミングは、農家の生活パターンを考慮して決定する必要があります。
一般的に、農家は早朝から農作業を開始し、夕食後の時間帯にFAXを確認することが多いため、夕方から夜にかけての送信が効果的です。
季節性も重要な要素となります。農繁期の春から秋にかけては農作業に忙殺されるため、FAXを読む時間が限られます。
一方、農閑期の冬場は時間に余裕があり、設備投資の検討も活発になるため、重点的な配信時期として活用すべきです。
送信頻度については、月1回程度の定期配信が適切とされています。あまり頻繁すぎると迷惑に感じられる可能性があり、逆に間隔が空きすぎると印象に残りにくくなります。
継続的な情報提供を通じて農家との接点を維持し、商談機会の創出につなげることが重要です。
農産業向けFAXDMの配信プランと料金
ValueFAXでは、お客様のニーズに応じた柔軟な配信プランをご用意しています。小規模テスト配信から大規模な全国配信まで、さまざまな規模に対応可能です。
初回配信では効果測定を重視したテストプランをご提案し、レスポンス状況を見ながら本格配信へと段階的に拡大していくアプローチを推奨しています。
配信料金は配信件数に応じた従量制となっており、1件あたり2.3円からご利用いただけます。
また、定期配信をご契約いただくお客様には、特別割引料金でのご提供も可能です。
原稿制作費、リスト作成費、配信作業費を含めたパッケージ料金もご用意しており、コストパフォーマンスの高いサービス提供を実現しています。
お見積もりは無料で承っておりますので、配信件数や頻度をお聞かせいただければ、詳細な料金プランをご提案いたします。
サポート体制とアフターフォロー
ValueFAXでは、専任の営業担当者がお客様の配信開始から効果改善まで一貫してサポートいたします。
配信前の戦略立案から原稿制作、配信実施、効果分析まで、すべての工程で専門的なアドバイスを提供し、お客様の営業成果向上を支援いたします。
このデータをもとに、次回配信に向けた改善提案を行い、継続的なPDCAサイクルの実現をサポートいたします。
また、お客様から寄せられるご質問やご要望に対しては、専門スタッフが迅速かつ丁寧に対応いたします。
配信システムの操作方法から効果的な原稿作成のコツまで、幅広いサポートを通じてお客様の営業活動の成功を全力でバックアップいたします。
まとめ
農業業界での営業活動を成功させるためには、業界特有の課題や顧客ニーズを深く理解し、適切なアプローチ方法を選択することが重要です。
特にFAXDMは農業従事者との接点づくりに効果的な手法として注目されています。
効率的な農業営業を実現するために、ぜひ本記事でご紹介した内容を参考にしてください。

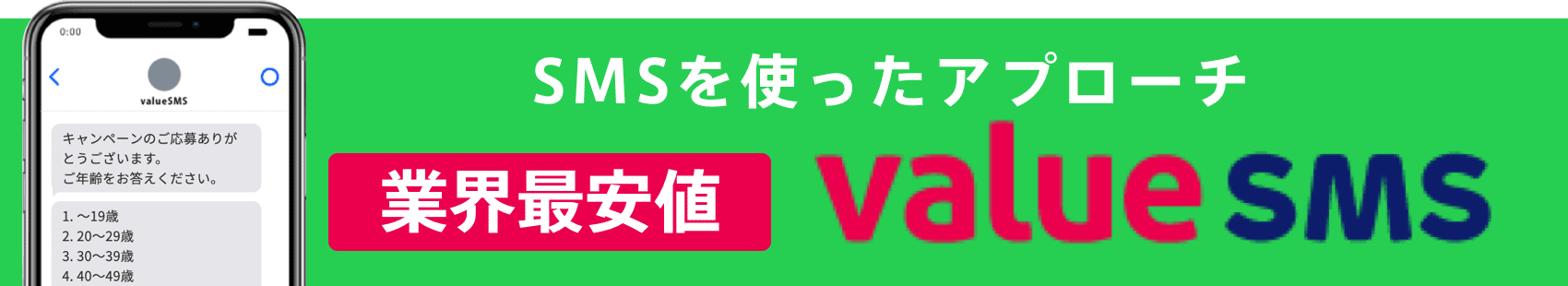


 資料請求・お問合せ
資料請求・お問合せ
 会員登録
会員登録